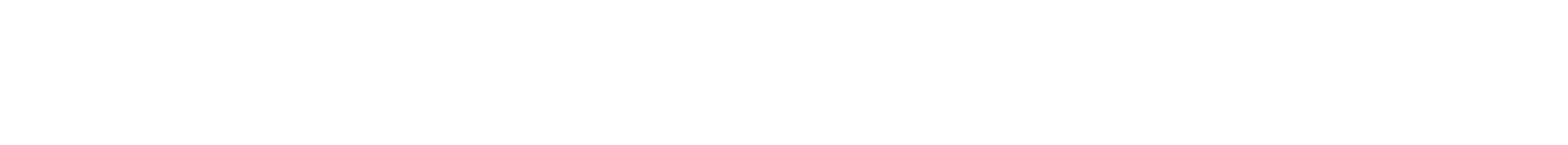名古屋市国際展示場(以下、ポートメッセなごや)では、大規模催事開催時のトイレや飲食店の混雑が課題となっています。特にコンサート開催時には特定のトイレに利用が集中し、他のトイレが十分に活用されない状況が発生。スムーズな施設利用を妨げる要因となっており、利用者の満足度低下が懸念されています。
この課題に共感したのが、東海テレビ放送株式会社(名古屋市東区)と株式会社アドインテ(京都府京都市)です。名古屋市とともに、高機能ビーコン「AIBeacon」を活用したトイレの混雑状況の把握・改善に向けた実証実験を進めています。
前回の活動では、ポートメッセなごやがある金城ふ頭エリアに13台のAIBeacon端末を設置し、トイレ周辺の混雑状況を計測しました。ビーコンで混雑を判定する対象範囲を5mに設定してデータを収集したところ、実際の混雑状況と異なる結果が得られるケースが発生。そこで、設定を調整し判定範囲を1mに変更した結果、現場の状況と計測値の乖離を抑制し、より正確なデータ取得が可能となりました。
今回の活動では、混雑状況表示の判定基準について検討しました。混雑状況周知用のウェブサイトでは、ビーコンで計測される周囲のスマートフォン台数が一定数(閾値)を超えると、表示を「空き」から「混雑」に切り替えています。閾値が高すぎると混雑していても「空いている」と表示され、逆に低すぎると実際には余裕があるのに「混雑」と表示されてしまう可能性があります。どのような基準を設ければ正確な混雑情報を来場者に届けられるのか検討を重ねた結果、トイレの場所によっても最適な閾値は異なることが現地の観察から明らかになりました。
例えばトイレの前を通行する人が多い場所では、トイレ利用者だけでなく、通行人や連れ添いの待機者も計測値に多く含まれるため、これを加味して閾値を高めに設定しておく必要があります。状況を正確に把握するため、5分おきにトイレ前の行列の人数を目視で記録する作業を2時間ほど実施し、各時刻の計測値と比較して実感覚と合う混雑判定の閾値を探索しました。食堂周辺や駐車場近くのトイレなど、場所ごとに混雑の特徴が異なり、結果として最適な閾値は場所により2倍程度の幅があることが分かりました。


◀通行人が少ない場所(左)と通行人が多い場所(右)では最適な閾値が異なる
このような検証を重ねることで、ようやく実態に即した混雑状況表示が可能となってきました。今後もより正確な混雑情報を提供できるよう、検証を続け改善を図っていきます。